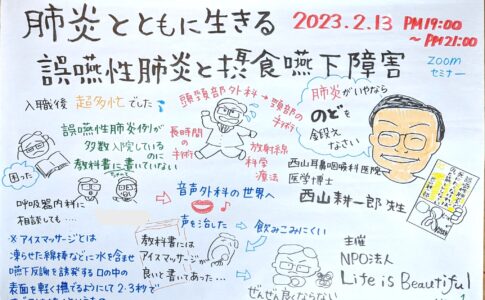佐々木理事 2023年 5月28日 Facebook記事より
がんで治癒困難な状況になったらどこで過ごしたいか。
一般市民、医療看護専門職を対象に行われた意識調査では、約7割ができれば自宅でと答えている。しかしその願いが叶う患者は現状2割に過ぎない。
がん患者の在宅緩和ケアを阻む要素は大きく3つあると考える。いずれも薬剤師が課題解決に大きく寄与しうる。
1. 不十分な意思決定支援
治療を中止して自宅に戻る。この決断のためには病状経過の見通しを共有し、その先の最善の選択を共に考える必要がある。しかし医療が進化する中、「やめどき」の判断はより難しくなりつつある。在宅緩和ケア導入時点においても、自分の予後が厳しいことをきちんと伝えられていない患者はいまだ少なくない。
2. 不十分なケア体制
病院から在宅チームに療養支援担当が変化する。これは患者にとっては大きな不安だ。この時期のシームレスなケア移行が非常に重要になる。在宅医療導入後、がん患者の病状は急速に変化していく。それを予見し、家族や介護者に過度の負担をかけないフレキシブルな支援体制が必要になる。
3. 不十分な緩和医療
緩和ケア病棟のように24時間モニタリングはできない。アドヒアランスにより制限された選択肢の中で、十分な苦痛の緩和を保証せねばならない。不足も過剰も患者・家族を苦しめる。迅速・頻回・長時間の対応が求められることも少なくない。患者・家族はもちろん個々の専門職にかかる負担も大きい。
治療技術の向上で、がんとともに生きる期間も延びている。5年生存率は7割に、10年生存率も6割に届こうとしている。そのような中、患者の苦痛の重点は、身体面・精神面から社会面のものへとシフトしていく。
終末期のみならずどんどん伸びていく生活期=がんとともに生きる時間をどう支えるのか。これも在宅緩和ケアとして考慮すべき課題だ。また、がん患者は診断、手術、化学療法、合併症治療、緩和医療、在宅医療とその都度、主治医が変わる。このような医療提供体制の中で、継続的に関われる医療専門職の存在は重要だ。制度としての家庭医、機能するかかりつけ医が存在しない現状、平時から最期まで関わりを続けられる可能性のある医療機関・医療専門職として薬局・薬剤師が果たせる役割もあるのではないだろうか。ここには大きな可能性が眠っているように感じる。
薬剤師さんたちは、一様に「動きたくても動けない」という。
知識はある。スキルもある。意欲もある。
それでも動けないのは、やはり「時間」と「お金」だ。
動いたことに対する対価がなければ、事業運営は成り立たない。薬局経営者も薬剤師を動かすわけにはいかないだろう。単価の安い仕事を数多くこなすことでしか収入が得られない。結果、薬剤調製という対物業務に時間の多くを取られてしまう。
変化していく地域のニーズ、患者のニーズに応じて、薬剤師のみならず医療専門職はその果たすべき役割を見直す必要があるし、それを後押しする制度設計も重要だと思う。
厚労省の松下さんからは、薬局・薬剤師に対してCSR(企業の社会的責任)、ノブレス・オブリージュ(noblesse oblige:「位高ければ徳高きを要す」)という考え方も示された。これらは専門職のプライドをくすぐるキーワードだ。
しかし、私企業や個人の善意や犠牲に基づく対人援助はケアの質や持続可能性の確保ができないし、責任の所在が不明確になる。求められる責任と役割に対し、診療報酬(介護報酬)上の相応の評価を確保することもやはり重要であろうと思う。
「お薬を配達する」のではなく「在宅での最適な薬物療法を支援する」、そして在宅診療チームの一員として、がんの在宅緩和医療など高度な患者ニーズに確実に応える。
提供される価値に応じた評価があれば、薬剤師の業務は調剤業務を基軸としながらも、おのずと対物から対人にシフトしていくのだろうと思う。
全国6万というコンビニを超える拠点数の調剤薬局。
そして30万人というOECD加盟国の中で人口当たりダントツ最多の薬剤師。
6年制の専門教育を受けた若い薬剤師の割合も増えている。
これは貴重な日本の社会資源。
在宅医療・在宅緩和ケア・在宅終末期ケアのニーズの増大に応えていくために、薬局・薬剤師の力をいかに引き出していけるのか。とても重要なテーマであるように思う。今日は神戸で開催された第16回日本緩和医療薬学会/学会委員会企画シンポジウムにパネリストとして登壇、ショートプレゼンテーションとディスカッションに参加させていただきました。貴重な機会を頂戴しました塩川満先生、小林さんはじめ、関係者の皆様、本当にありがとうございました。