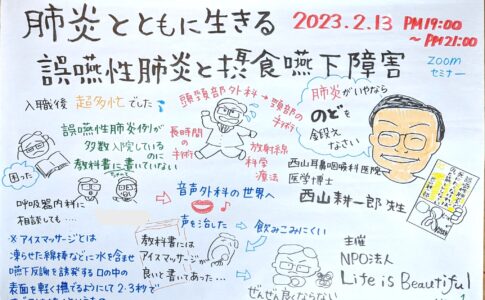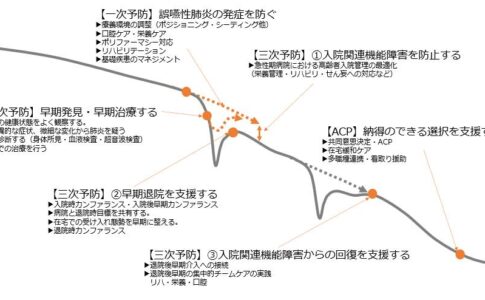佐々木理事 22年11月11日 Facebook記事より
出会いはFacebook。
人工呼吸器をつけて生活しているのに、すごくポジティブな発信をされていて、講演でICF(生活モデル)の実践ケースとして紹介させてもらえないか、そんな相談をきっかけにつながらせていただいた。
そして、2年前。はじめて玄三さんのご自宅を訪問した。実際にその暮らしぶりを見せてもらって、2つのことに感銘を受けた。
いずれも、建前上は当たり前だが、現実には難しく多くの人が諦めている(諦めさせている)こと。しかし玄三さんたちは、それをしっかりと実現していた。1つ目は「病人を世話する」ではなく、「生活を継続する」が実践されているということ。
主語がケア提供者ではなく、あくまで本人なのだ。そして、その生活は本人だけのものではないということ。時間や空間を共にするみんなで共有されている。だからこそ、本人のわがまま(WANTS)を叶える、というよりは、みんなの生活をみんなで支え合う。
その中で、誰もが納得できるところに自然に落ち着いていく。そのためには、本人、家族、そしてそこでの生活に関わる全ての人が対等に意見を言い合える環境が必要になる。玄三さん「たち」は、そんな心地よい関係性の中で、充実した生活を楽しまれていた。ちなみに玄三さんは、日中、パジャマで過ごすことはない。ぴしっと服を着て過ごしている。もちろんコーディネートにもこだわる。欲しい服を自分で選び、Amazonで買う。ヘアスタイルも気になるし、口腔ケアも衛生面のみならず審美面にも気を配る。
中野さんと半日一緒に過ごしてみると、「人工呼吸器を装着している最重度身体障害の神経難病患者」ではなく、ちょっとイケてるオジサンに見えてしまう。2つ目は、たとえ医療的なケアであっても「専門家にお任せ」ではなく、本人自ら、自分にとって最適な形を主体的に考え、挑戦し続けるということ。
そもそも神経難病の人がどういうケアを必要としているのか、一番わかっているのは本人のはずだ。専門家の「こうすべき」、「これがいいはず」、「これしかできない」をただ受け入れるのではなく、本人が、自分にとって最も合理的で快適なケアを専門家と一緒に考えていく、一緒に試していく。
「本人にとってのよりよい生活」を継続するためには、このプロセスは必須だ。例えば食事。
玄三さんの食事のスタイルは独特だ。気管食道分離手術をされているので食物の誤嚥・窒息は起こらないとはいえ、基本的は球麻痺に近い。舌の運搬能力は非常に低下している。しかし、咽頭まで届けば、あとは重力の力で食事は胃に落ちていく。玄三さんは、車いすから身体を前に倒し、テーブルに置かれた台に前額部(オデコ)を置き、上半身を支える。椅子の上でお辞儀をしているような姿勢だ。
その状態で、下向きで食事をする。最初に見たときは「え? なんだこれ?」と思った。しかし、玄三さんは、その姿勢でどんどん食べていく。普通の人と同じくらいの食事を、普通の人と同じくらいのペースで(約15分間)完食してしまった。玄三さんはラーメンを食べるときの姿勢から、この体位を思いついたのだという。よくよく考えてみれば、これは食支援でいうところの「攻撃姿勢」だ。
食事をするうえで、安全かつ効果的な姿勢なのだ。しかし、まさか神経難病の人がこの姿勢を維持できるとは誰も思わない。玄三さんは、自ら食事に最適な姿勢を考え、その姿勢を無理なく維持するための補助具を自分たちで作り、自らの嚥下機能に応じた食介助の方法、食形態の調製方法をヘルパーさんたちと見つけ出した。そして、創意工夫と試行錯誤を重ね、摂食嚥下障害を克服してみせたのだ。飲水は逆の姿勢を取る。少し体を後ろに倒して、舌の上から口腔内に水分を流し込む。と同時に下唇を持ち上げて閉口させると、玄三さんは「誤嚥をする要領で」重力の力も借りながら飲み込んでいく。これも非常にスムースだ。200ml程度の水分をあっという間に飲み干してしまう。玄三さんのベッドはワークスペースになっている。
ベッドを快適な角度にギャッジアップすると、作業用PC、コミュニケーション用PC、そしてテレビの3つのディスプレイが重複なく視界に入るようになっている。下肢の残存機能を生かして、2つのマウスを同時に操作する。左足はクリック用、右足はカーソル用。それぞれを微細に動かしながら、すいすいとPC作業をこなしていく。もちろんベッドの上で、しかも足でマウスを操作するためにはいろんな工夫が必要だが、ここに必要とされるのは図画工作の才能。
パソコンや両面テープなど、身近な材料で快適な作業のための設備を自作されていた。病気や障害を理由に大切にしてきたことを諦めない。諦める必要はない。玄三さんは自らの暮らしぶりを通じて、そんなことを教えてくれたような気がする。これは高齢者の在宅ケアにおいても、参考になることが多い。
「どういう介護をするか」の前に、「どういう生活を送りたいのか」をもう一度、じっくりと考えてもらってもいいのかもしれない。
高齢者のケアは、①本来は「生活の継続」が目的だ。②その生活は「本人の選択」が尊重されるべきだし、③その生活を送る上では「本人の強み」が発揮されることが重要だ。これが高齢者福祉の三原則だ。
日本では、生活の継続といいつつ、目先の事故が起こらないリスクヘッジ中心の「医学モデル的管理」が行われることが多い。本人の強みを生かす、というよりは、本人の弱みをいかに埋めるかが本人不在の環境で議論され、ケアプランが立案される。
いま一度、その人、その家族にとっての「生活」を見つめなおしてみる。その人が「生活」を共有しているコミュニティの範囲(必ずしも同居家族だけとは限らない)、そして、その「生活」における優先順位、このあたりをしっかりと把握できれば、支援のあり方も変わってくるかもしれない。
「生活モデル(Social Model)」や「ICF(国際生活機能分類)」などキーワードばかりが先行するこの領域において、それってつまりどういうこと?を具現化したのが玄三さんたちのライフスタイル(敢えて療養生活とは呼ばない)。僕も講演の中で、玄三さんの存在を1つの事例としてご紹介させていただいてきたが、実際に自分の目でみて(さらに飲水介助までさせていただいて)「生活を継続する」という言葉の意味を、実体験として理解できた。たぶん、在宅ケア、施設ケアに関わる人の中には、「病気や障害とともに生きる」、そしてそれを支えるとはどういうことなのか、具体的なイメージがつかめていない、あるいは、どうすればそれができるのかわからない、という人も少なくないと思う。明日、土曜日の午後。ぜひ一人でも多くの人に玄三さんの話を聞いてほしい。介護観が180度変わると思う。